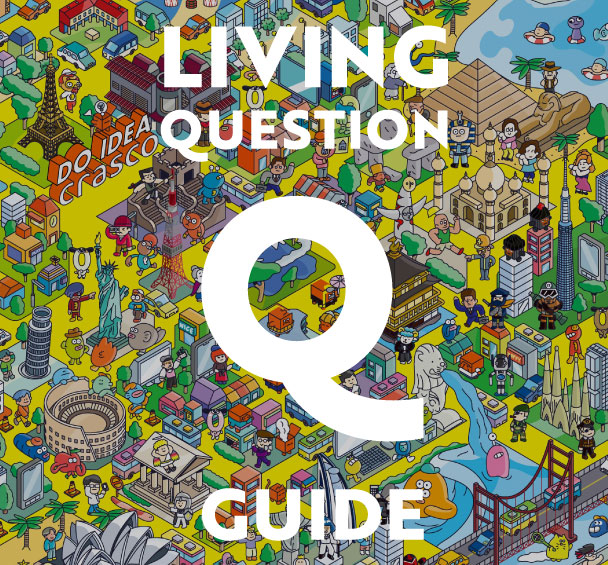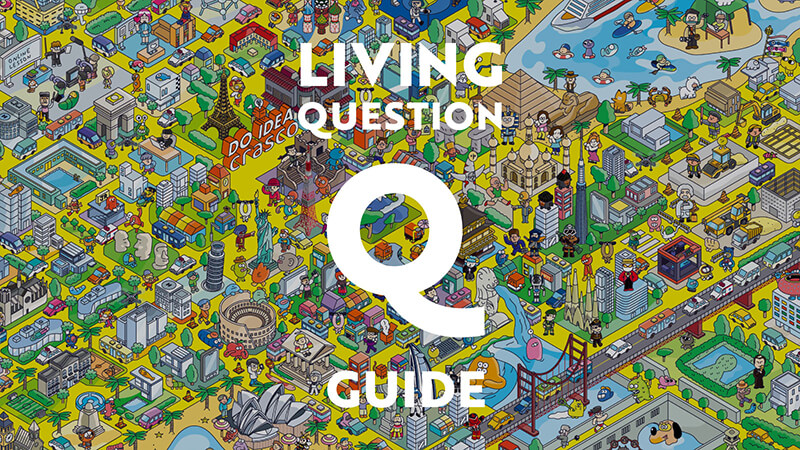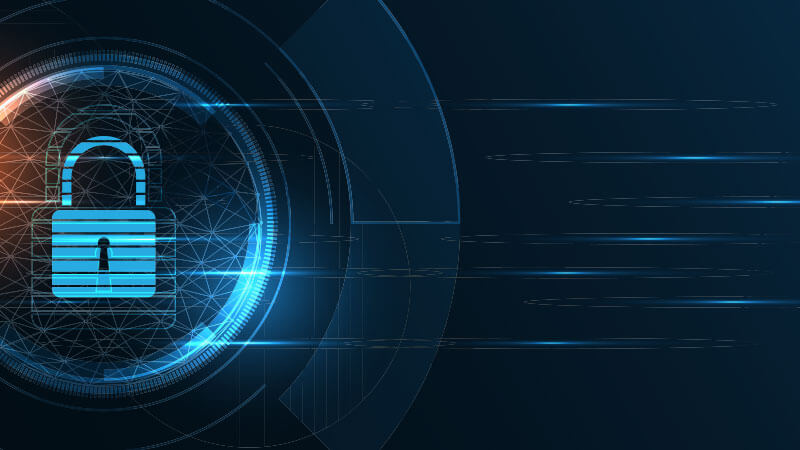【経営者の視点】科学が解き明かす「運の良い人」の共通点と、それを組織に活かす方法
- 経営者の視点
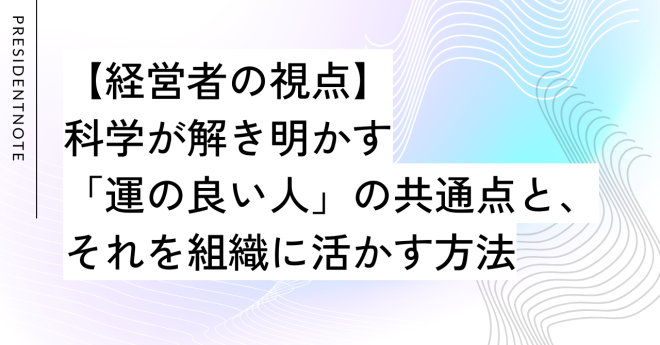
導入:運を科学する視点
「運が良い」という言葉は、どこか曖昧で捉えどころのないものとして語られがちです。私も、日々の業務や人生の岐路において、「運」の存在を感じることは少なくありません。しかし、書籍(化学がつきとめた運のいい人)で紹介(以前のブログ記事参照)させてもらったように、運を単なる偶然や幸運として片付けるのではなく、科学的な視点から分析し、それを自らの行動や思考によって引き寄せることができるという考え方は、経営者として非常に興味深いものでした。
運の良い人の特徴:自己理解と強みの活用
書籍では、運の良い人は自分の個性を理解し、それを最大限に活かす方法を知っていると述べられています。これは、組織運営においても非常に重要な示唆を与えてくれます。経営者は、まず自身を含めた組織メンバー一人ひとりの個性や強みを深く理解する必要があります。そして、それぞれの能力が最大限に発揮できるような環境を整え、適材適所を実現することが、組織全体の「運」を高めることに繋がるのではないでしょうか。
例えば、積極的に新しいことに挑戦する意欲のある社員には、新規事業の立ち上げを任せる。論理的な思考力に長けた社員には、データ分析や戦略立案を担ってもらう。それぞれの個性を理解し、適した役割を与えることで、個々の能力が最大限に引き出され、結果として組織全体の成果、つまり「運」が向上すると考えられます。
自己受容:ありのままの自分を活かす
「人は自分を変えることによって運を悪くすることがある」という指摘は、自己啓発や能力開発が推奨される現代において、一見すると逆説的に聞こえるかもしれません。しかし、これは自身の本質を否定し、無理に理想像に近づこうとすることが、かえってストレスを生み、本来持っている力を発揮できなくしてしまう、ということを示唆しているのではないでしょうか。
経営者として、社員に対して成長を促すことは重要ですが、同時に、彼らの個性や強みを尊重し、それを活かすことを考えるべきです。短所を克服することにばかり目を向けるのではなく、長所を伸ばし、それを組織の力に変えていく。そうすることで、社員は自信を持って仕事に取り組むことができ、結果として良い「運」を引き寄せやすくなるのではないでしょうか。
「しあわせのものさし」:組織としての幸福を定義する
運の良い人は、自分なりの幸福を測る基準を持っていると言います。これは、組織においても同様のことが言えるのではないでしょうか。売上や利益といった定量的な目標も重要ですが、それだけが組織の幸福ではありません。社員の働きがい、顧客からの信頼、社会への貢献など、組織としての「しあわせのものさし」を明確に定義し、それに基づいて行動することが、長期的な成功、つまり「運」に繋がると考えられます。
例えば、クラスコでは「世界中に『人生楽しい人』『ファン』を増やす」というビジョンを掲げています。これは、私たち自身の幸福だけでなく、関わる全ての人々の幸福を追求するという、組織としての「しあわせのものさし」です。この基準に基づいて事業を展開していくことが、結果として私たちの「運」を高めているのかもしれません。
運を自ら作り出す:ポジティブな信念と行動
「運は自分で決めるもの」という考え方は、経営者にとって非常に勇気づけられるものです。困難な状況に直面した時、それを単なる不運として諦めてしまうのではなく、「自分は運が良い」と信じ、努力を続けることで、状況を好転させるチャンスを掴むことができる。この信念を持つことが、成功への原動力となるのではないでしょうか。
また、運の良い人は、常に新しいことに挑戦し、行動し続けていると言います。これは、経営においても非常に重要な姿勢です。変化を恐れず、積極的に新しい事業に挑戦したり、既存の事業を改善したりすることで、予期せぬ幸運、つまり「セレンディピティ」を引き寄せることができる可能性が高まります。
運の良い人々との関わり:ポジティブな影響を組織へ
運の良い人の近くにいることで、その行動パターンを学び、自分自身も運が良くなる可能性があるという指摘は、組織づくりにおいても示唆に富んでいます。積極的に外部の成功者や、異なる分野で活躍している人々と交流を持つことで、新たな視点や刺激を得ることができ、組織全体の「運」を高めることに繋がるかもしれません。
また、組織内においても、常に前向きで、困難な状況でも諦めずに努力する社員を評価し、ロールモデルとすることで、組織全体の雰囲気をポジティブに変え、良い「運」を引き寄せやすくすることができます。
他者との共生:利他的な行動がもたらす幸運
運の良い人は他者を思いやり、共同体として生きることが重要であると言います。これは、CSR(企業の社会的責任)の重要性が増している現代において、企業経営においても重要な視点です。目先の利益だけを追求するのではなく、社会全体の利益を考え、利他的な行動をとることが、結果として企業の信頼を高め、「運」を呼び込むことに繋がるのではないでしょうか。
例えば、地域社会への貢献活動や、環境問題への取り組みなどは、直接的な利益には繋がらないかもしれませんが、企業のイメージ向上や従業員のモチベーション向上に繋がり、長期的な視点で見ると、企業の「運」を高める可能性があります。
セレンディピティ:目標設定と柔軟性
偶然の幸運をキャッチする能力、セレンディピティは、明確な目標を持つことで高まると言います。これは、目標なき航海では、どんな幸運も活かすことができない、ということを示唆しているのではないでしょうか。明確な目標を持つことで、私たちは常にアンテナを張り、目標達成に繋がる情報や機会を敏感に察知することができます。
しかし、同時に、運の良い人は、予期せぬ出来事や変化にも柔軟に対応できると言います。計画通りに進まないことがあったとしても、それをチャンスと捉え、柔軟に方向転換することで、思わぬ幸運を掴むことができるかもしれません。
ゲームを降りない:長期的な視点と粘り強さ
運の良い人は、自分の夢や目的に対して、長期的な視点を持ち、ゲームから降りないと言います。これは、経営者にとって最も重要な資質の一つかもしれません。短期的な成果に一喜一憂するのではなく、長期的な視点に立ち、困難な状況でも諦めずに目標に向かって進み続ける粘り強さが、最終的な成功、つまり「運」を引き寄せるのではないでしょうか。
また、運の良い人は、プラスとマイナスの出来事を均等に受け入れると言います。成功体験に奢ることなく、失敗から学びを得て、それを次のステップへの糧とする。この謙虚さと成長意欲を持ち続けることが、長期的な「運」を味方につける秘訣なのかもしれません。
まとめ:運を科学し、組織と人生を豊かにする
今回の書籍の内容を通して、運は決して偶然や曖昧なものではなく、自身の思考や行動によってコントロールできるものであるということを改めて認識しました。そして、その考え方は、個人の生き方だけでなく、組織運営においても非常に重要な示唆を与えてくれるものです。
経営者として、組織の「運」を高めるためには、メンバー一人ひとりの個性を理解し、強みを活かすこと、組織としての幸福を定義し、共有すること、そして、長期的な視点と粘り強さを持つことが重要だと感じました。
もちろん、運の要素を全てコントロールできるわけではありませんが、科学的な視点から運を理解し、日々の行動を意識することで、より良い結果を引き寄せることができる可能性が高まります。この知識を、自身の人生、そして組織運営に活かし、「運が良い」と言えるような豊かな未来を創造していきたいと思います。