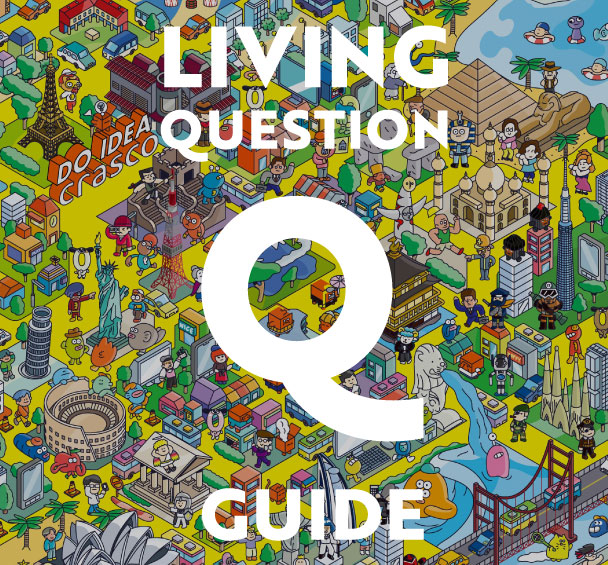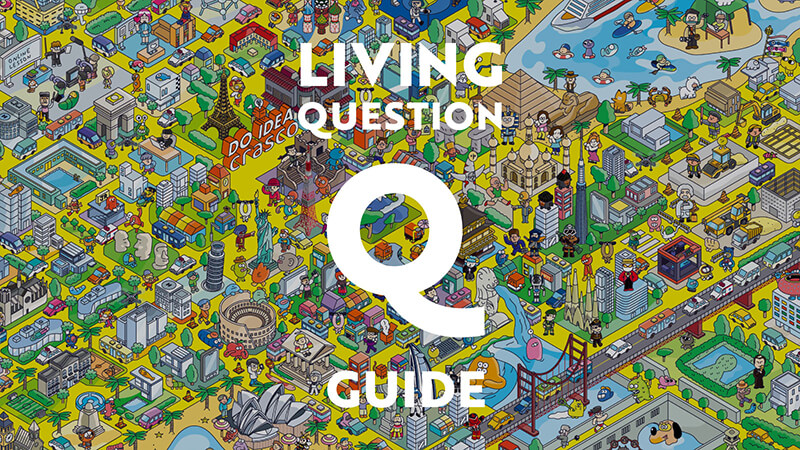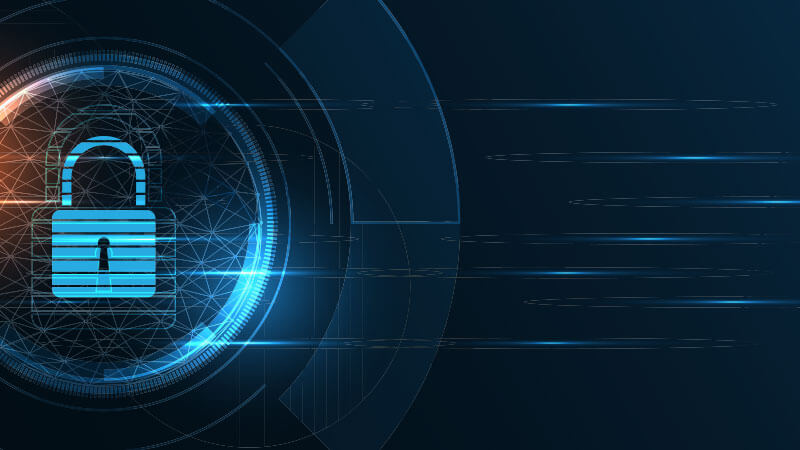マネージャーに送る言葉08
- 未分類
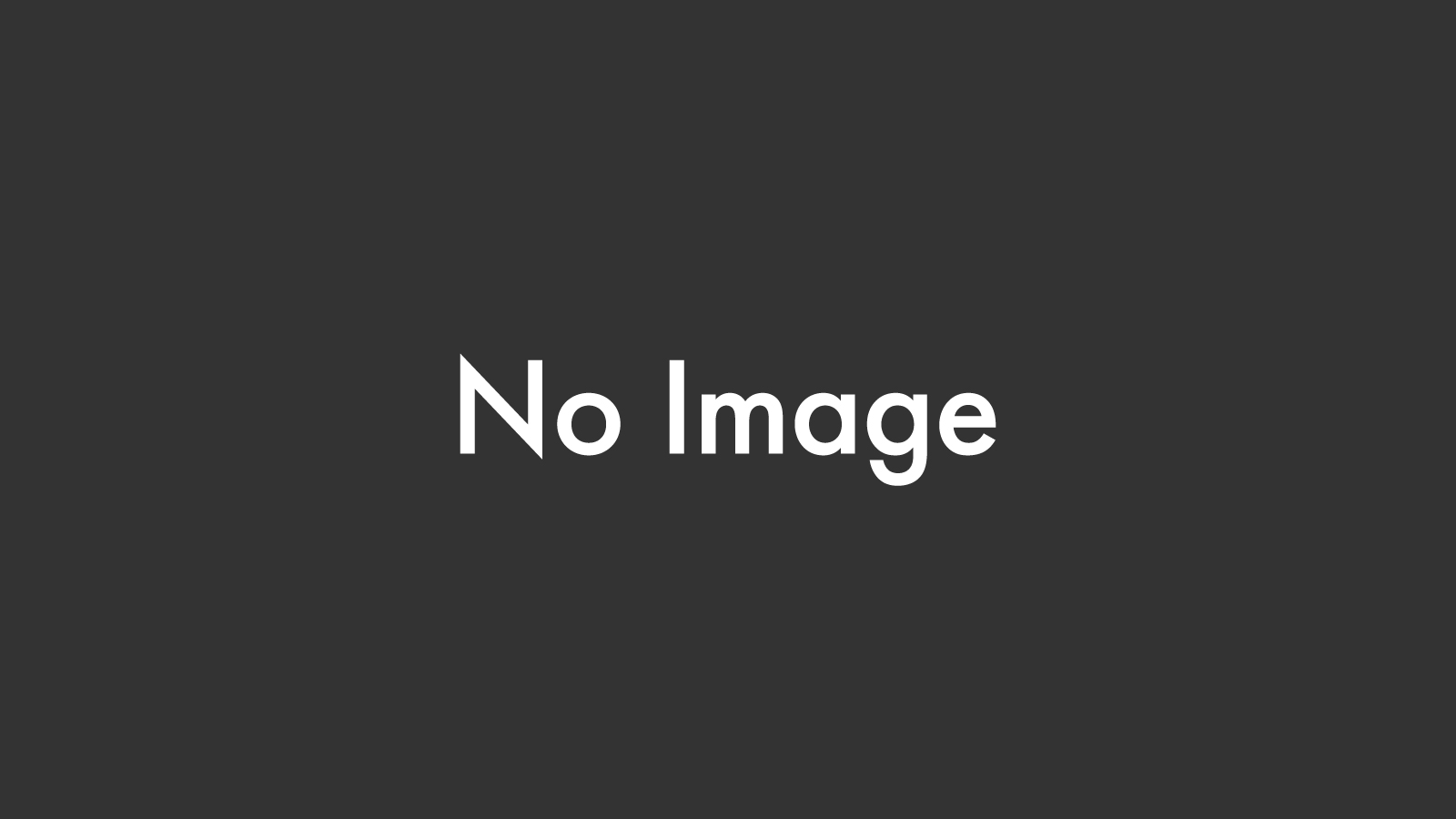
これも現場ではよく起こることです。
まさに本人たちは頑張ってるがなかなか結果が出ない状態。
例えば、一人で仕事をする場合は、その手順や判断基準など、頭の中にあれば事足りて、何か問題が起きても個人の判断でどんどん進めていくことができ、情報を共有することも必要ありません。
しかし、人員が増えるとそうはいきません。
まだ2~3人程度であれば、目も行き届き、声掛けでコントロールできますが、人の数が5人を超えるともう把握することも難しくなり、統率が取れなくなります。
そうなると、もう大変です。
個々が自分の感覚や基準で仕事を判断し、業務の量が多ければ多いほど、仕事が矛盾だらけで、中途半端。
勝手に「ここまでが自分の仕事」とか「自分のやり方はこれでいい」など…
結局「業務が複雑になり」時間がかかり、それぞれのやり方で進めているので、品質もバラバラ、やり直しの仕事も増え、結局時間ばかりを労することになります。
こうやって、仕事を「非効率的」にしているのは、「業務手順が不明瞭」「意思決定の基準がない」「判断が属人的」など、思いついたものを挙げたらきりがありません。
これは置き換えるとすべて「問題」です。
組織が大きくなったり、かかわる人が多くなれば、当然に「仕事のやり方」や「システム」、「ルール」、そして「考え方」を変えていかなければ、どこかに矛盾が生じてしまします。
現場で起こっていることを、常に見て、聞いて、確認して、これらの「問題」を、日々、改善、解決してく責任が、マネージャーにはあります。
「問題」には「大きな本質的な問題」「小さな目の前の問題」など、様々なレベルが存在します。「業務効率化」を考える際に、見つけやすいという理由から、つい「小さな目の前の問題」を解決することに注力して
しまう場合があります。
例えば、ある会社で膨大な量の帳票から必要な情報を探すのに時間がかかり、業務が非効率になっていたとします。
そこでシステム化を行い「膨大な帳票類への検索性を高めることを実現」したとしても、それが必ずしも本当の意味での業務効率化にはつながるとは限りません。
何故かというと、この会社で管理すべき情報か、そうではない情報かを精査するルールがなければ、管理すべき情報は日々増えていき、記録、確認に時間がかかり、業務はどんどん非効率になっていきます。
また、管理する帳票の様式を標準化することなく、それぞれの社員が勝手な様式を使ったとしたら、管理帳票の種類は増えていき、この場合も業務は非効率になっていきます。
「小さな目の前の問題」を解決しても、結局は前より業務が複雑になってしまうことは十分考えられます。
「業務効率化」を考える際には、常に「本質的な問題」を見つけることが大切で、その為には、「本質的な問題」に至るまで、現状をより確認、分析し、そこからゴールに向かってどのような対策を実現していくのか
を検討する必要があります。
重要なのは、「解決できるかどうか」よりも、そういったひとつひとつの「問題」に真摯に向き合い、本気で解決しようとする心構えをもっているかです。
本気で向き合えば、必ず解決の糸口が見つかったり、周りが手を差し伸べてくれたりと、状況が変わってきます。
最悪なのは、その大変な状態や「問題」をわかっているのに、「仕事の量が多いから仕方がない」「仕事が難しいから仕方がない」など、もっともらしい理由をつけて
「何も考えない」「何も行動しない」そんなマネージャーです。
でもそんな現状に気づいて一歩でも前に進もうと思うのなら、不器用でも本気で行動すれば、何かが変わるはずです。
大きな成長も、まずは小さな一歩から始まるんです。