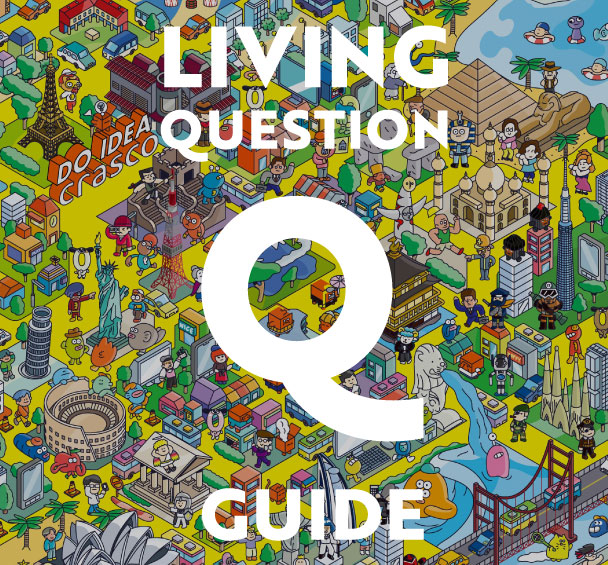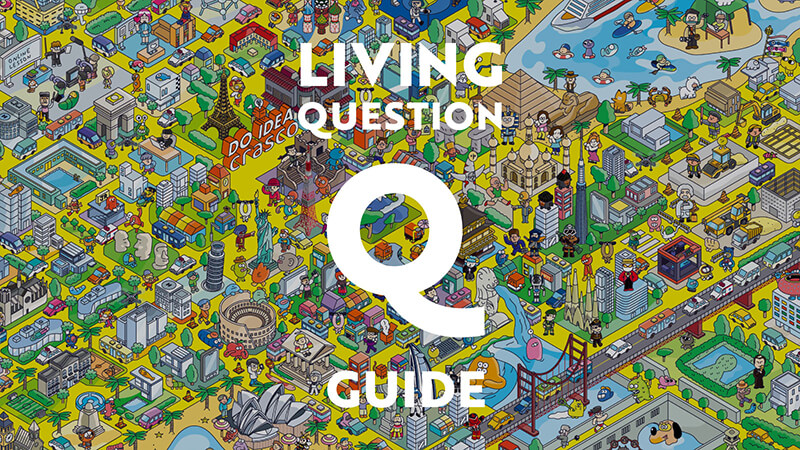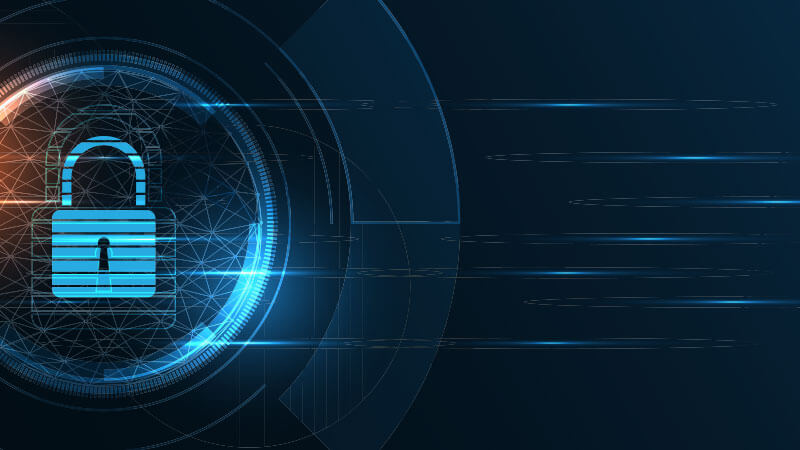118年ぶりの民法改正。
- 未分類
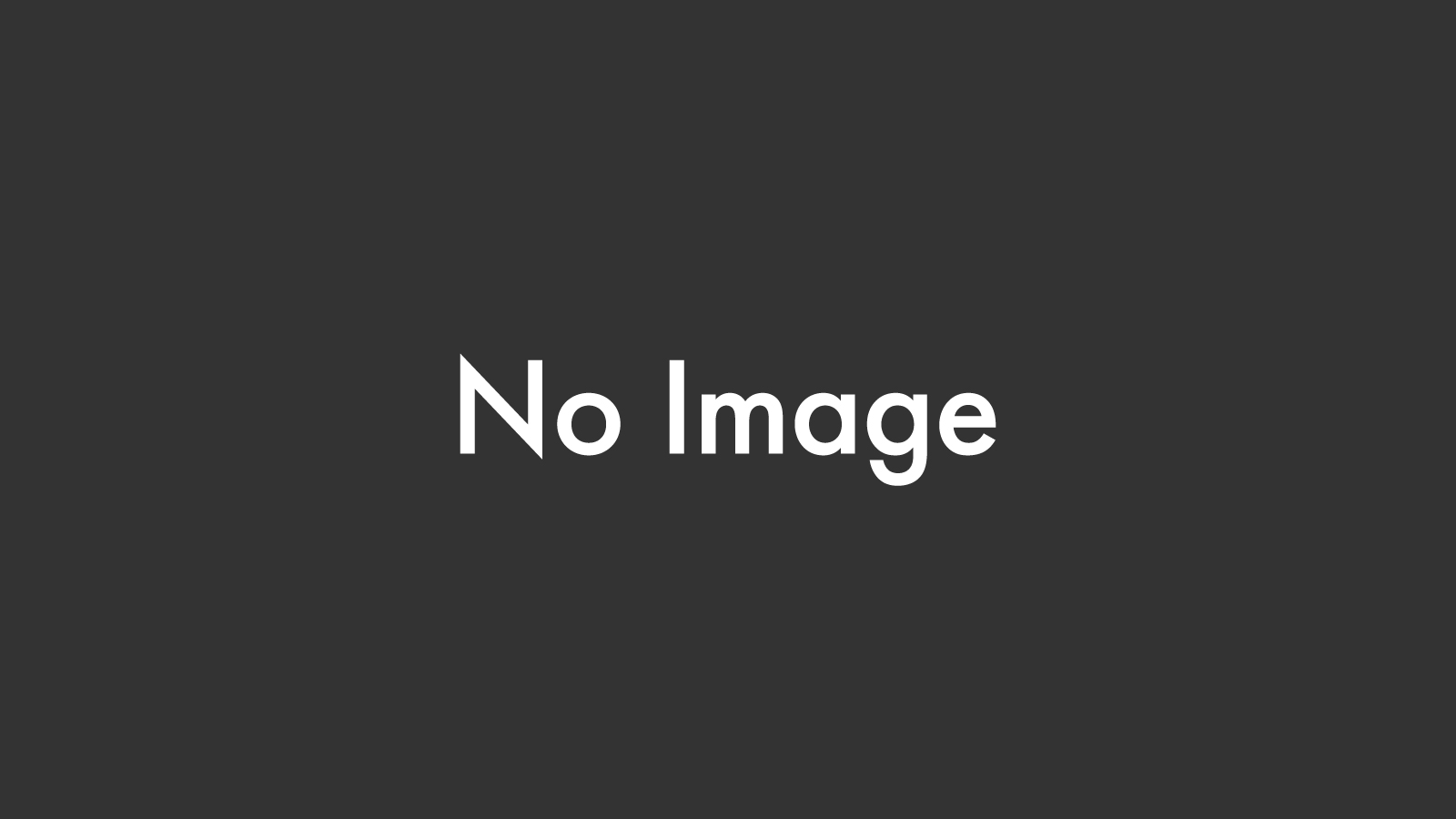
118年 ぶりの民法大改正に向けての改正原案が先月まとまり、来年2月に正式な案として、通常国会にて議論されることとなります。
今回の民法改正では、消費者が企業に比べて弱い立場にあるとして消費者を擁護する姿勢を強めた方向性となっています。
その一例として
□法定利率の引き下げ
現在、5%の固定金利から、3%に変更。その後3年毎に1%刻みで見直し。
□事業の連帯保証
企業への融資で、契約に詳しくない経営者の家族らが連帯保証人となり、多額の借金を背負い生活が破綻する事態が少なくないことから。
家族等の第三者が個人で保証人になる際には、公証人が立ち会い、自発的な意思を確認することが条件となる。
このような事態は少なくなると思われるが、その分融資の条件が厳しくなることが予想されます。
□時効
債権の「時効」も見直しになり、現在は「飲食代は1年」、「弁護士費用は2年」、「診察料は3年」等と、支払う内容によって時効の期間が異なっていたが、「債権者が請求できると知った時から5年」に統一されます。
これにより、飲み屋さんのツケも5年に遡って請求ができます。
その他、電子契約等が増加したことから、「約款」に対する法整備が勧められたりと、特に債権関係、契約に関する規定の「現代化」が盛り込まれ、賃貸借契約や敷金の取り扱いなど、大きく影響が見込まれます。
賃貸に関する「民法改定案」については、それだけにフォーカスしてブログで書きたいと思います。
「民法改正」は、私たちの生活にも、ビジネスにも大きく影響するものですから、今後も動向を見守りたいです。