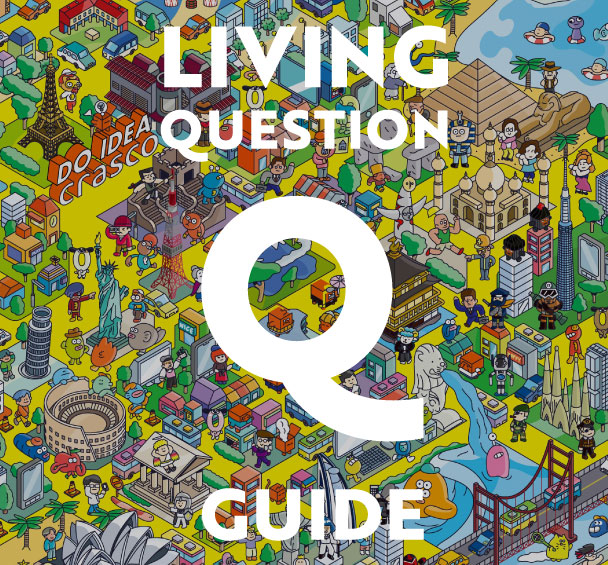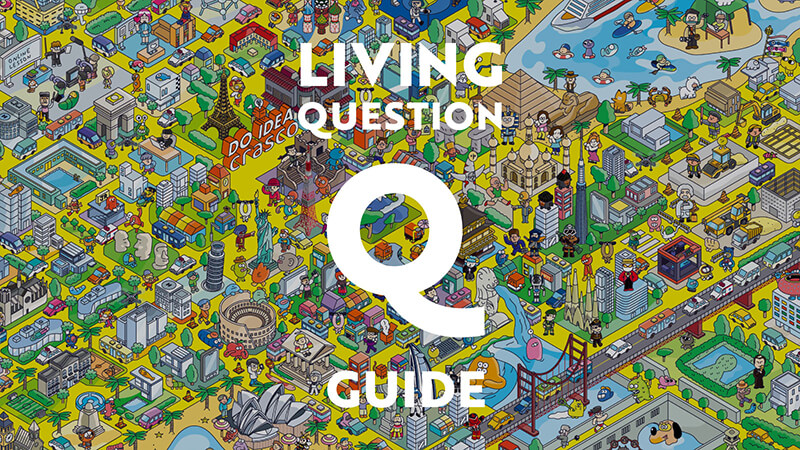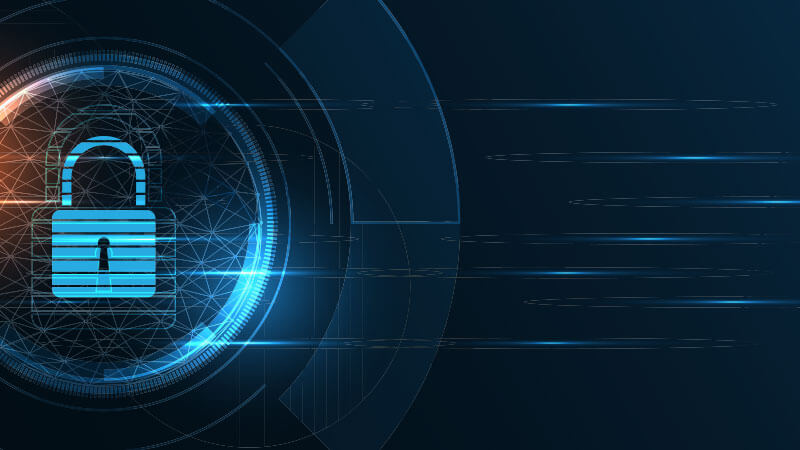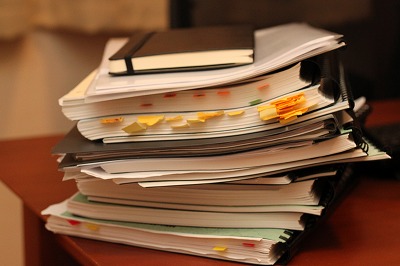詐欺師の話術は「マッキンゼー式」だった
詐欺業者らとのやりとりで気づいたことがあった。それは、彼らは自分たちの話を伝えるために、ことあるごとに「3つ」というキーワードを話の冒頭で話したことだった。
それで思い出したのが、経営コンサルティング会社、マッキンゼー・アンド・カンパニーだ。同社では顧客企業などへのプレゼン資料やトークにおいて「3」がマジックナンバーになっていることはよく知られている。
「ポイントは3つあります。1つめは――。2つめは――。3つめは――」
1つや2つでは「少ない」という印象のため説得力が小さくなるが、4つや5つもあると「話が長い」という印象が強くなり、相手は集中力が持続せず真剣に聞かなくなる。「3」という数字が、人間にとって最も受け入れられやすい数字なのだ。
このトークの手法は、主に自分の意図するところを相手に的確に伝えたい時に使われる。話し相手の頭の中に3つの枠組みを準備させて、そのひとつひとつに、こちらの伝えたいことを埋めていく。これにより、自分の話を相手にわかりやすく理解させることができるのだ。
特に、この手の競馬詐欺にひっかかるのは、競馬初心者である高齢者がほとんどである。仕込みレースというものを高齢者に理解させようと、それをいっぺんに話したのでは、とても理解してもらえない。そこで「3つ」という初心者にもわかるやすい形にして、話を複雑にせず、順を追って説明をする。
この業者の場合、仕込みレースなどというウソの話をもちかけているので、詐欺ということになるが、この説明のテクニックは、営業でもプレゼンでも一般のビジネスでも大いに使えるものである。
もし、なかなか自分の話が相手に伝わらないと感じている人は、相手の頭に3つの枠組みを用意させて、そこに要点を入れて話すように心がけてはどうだろうか。
「理由は3つあります」
「重要なことは3つです」
「お伝えしたいことは3点です」
そうやって話の冒頭を「決め文句」のようにして、あとを続ける。そうすれば相手は「なんだろう」と思い、耳を傾けるかもしれない。また、よく聞けば話の内容が陳腐であったとしても、不思議とそれらしく聞こえて、説得力がアップすることもあるのだ。(出展 プレジデント)
マジックナンバーを使用するとは
詐欺師も勉強しているのですね。
ちぇっと「なるほど」っと思ったので記載しました。