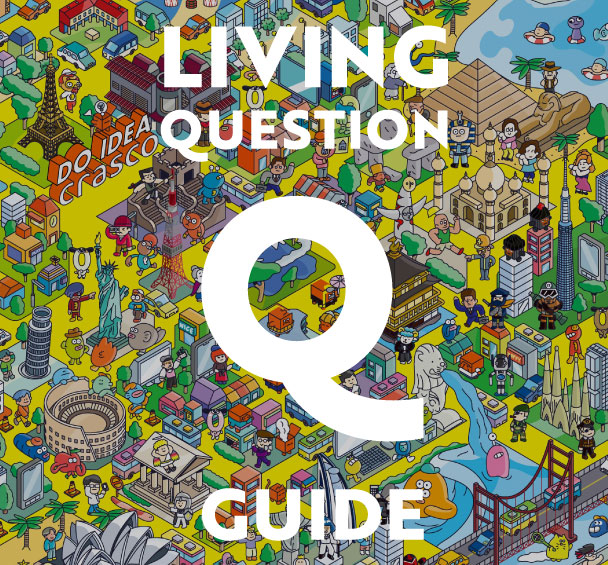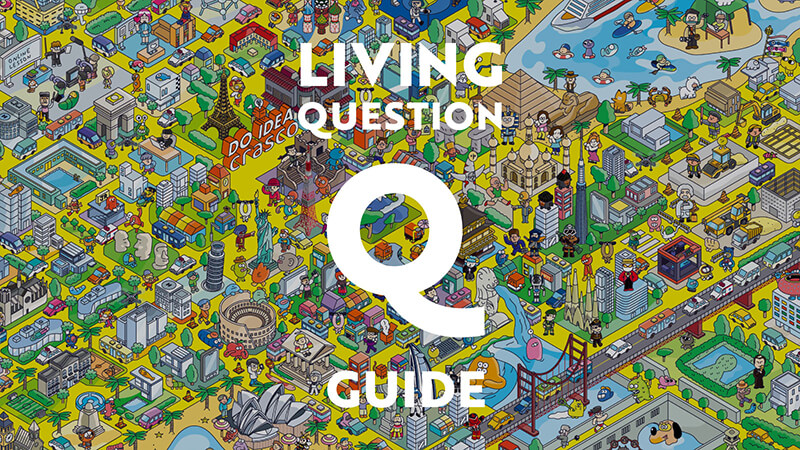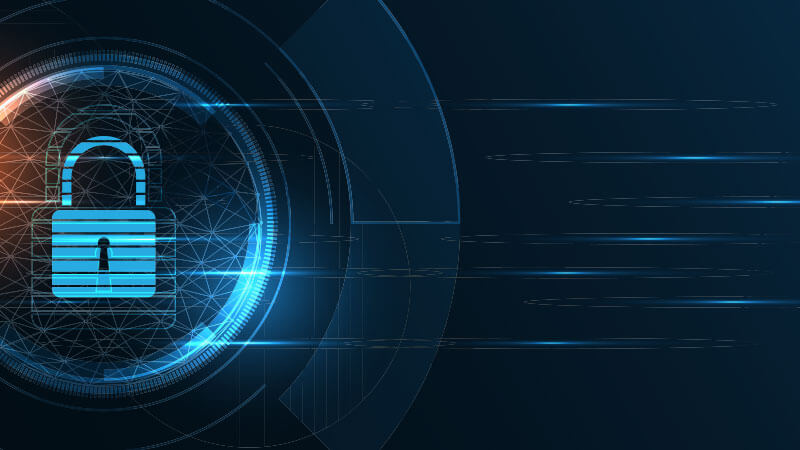【小村典弘】能登半島地震からの復興、住環境再建に向けたクラスコの挑戦と不動産業界の未来
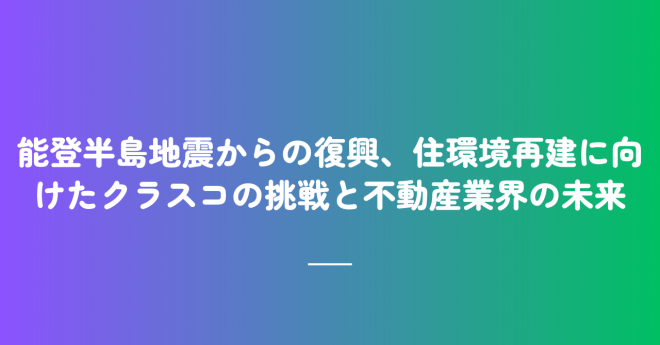
目次:
- はじめに:能登半島地震が突きつけた現実
- 地震直後の混乱とクラスコの初動対応
- 被災者支援の具体策:住環境の再建に向けて
- クラスコの支援活動から見えた課題と教訓
- 不動産業界が取り組むべき今後の対策
- 能登の復興、そして不動産業界の未来へ
- まとめ:困難を乗り越え、より良い未来を築くために
1. はじめに:能登半島地震が突きつけた現実
2024年1月1日、能登半島を襲った大地震は、多くの人々の日常を一瞬にして奪い去りました。人々の心には深い傷跡が残りました。石川県金沢市に本社を置くクラスコも、地震発生直後から対応に追われました。本社内も大きく揺れ、物が散乱する状況でしたが、何よりも気がかりだったのは、管理物件にお住まいの入居者様の安全でした。
新年の幕開けが、まさかこのような形で始まるとは、誰も想像していなかったでしょう。しかし、この未曾有の災害は、私たち不動産業界に、そして社会全体に、改めて多くのことを問いかけました。人々の生活の基盤である「住まい」の重要性、そして、災害に強い街づくりとは何か。私たちは、この経験を無駄にすることなく、未来へと繋げていかなければなりません。
2. 地震直後の混乱とクラスコの初動対応
地震発生直後、クラスコでは迅速に対策本部を立ち上げました。まず行ったのは、管理物件の被害状況の確認です。電話やメール、そして可能な範囲で直接訪問するなど、あらゆる手段を用いて入居者様の安否確認と被害状況の把握に努めました。
しかし、想像を遥かに超える数の問い合わせが殺到し、電話回線はパンク状態。電気や水道などのライフラインも寸断され、情報収集もままならない状況でした。そのような状況下でも、社員一人ひとりが「何かできることはないか」と考え、行動しました。被害状況の情報を共有し、優先順位をつけ、緊急性の高い案件から対応していく。まさに手探りの中での対応でしたが、クラスコが一丸となって困難に立ち向かった時間でした。
管理物件では、タイルの剥がれ、瓦の落下、壁の亀裂、給湯器の転倒による漏水など、様々な被害が報告されました。1ヶ月間で5600件もの不具合が発生し、その対応に追われる日々。応急処置を行いながら、二次災害を防ぐための安全確認も徹底的に行いました。この時、改めて感じたのは、日頃からの備えの重要性です。耐震性の高い建物であることはもちろん、万が一の事態に備えた入居者様への情報提供や、迅速な対応ができる体制づくりが不可欠だと痛感しました。
3. 被災者支援の具体策:住環境の再建に向けて
混乱の中、クラスコが最も重要視したのは、被災された方々の生活を一日でも早く、そして少しでも安全に取り戻すための支援でした。住環境に関わる企業として、私たちが提供できることは何か。社員一同で考え、以下の具体的な支援策を実施しました。
暮らしのお困りごとを解決するWEBサイトの開設
地震発生から間もない1月4日、クラスコは自社開発したノーコードツールを活用し、「地震問題解決マニュアル」を掲載した特設サイトを立ち上げました。電話が繋がりにくい状況が続く中、入居者様自身で比較的簡易な不具合に対応できるよう、漏水トラブルや家具の固定方法などを解説したマニュアルを公開したのです。
このサイトは、クラスコの管理物件にお住まいの方だけでなく、全ての方に無料で公開しました。公開から約1ヶ月で28,721件ものアクセスがあり、多くの方々が情報を求めていることを改めて認識しました。SNSでの拡散もあり、予想以上の反響をいただきました。この経験から、災害時には、正確で分かりやすい情報を迅速に提供することの重要性を改めて学びました。
「仲介手数料無料」と「家賃負担」による住居支援
住まいを失われた方々にとって、新たな住居を見つけることは喫緊の課題です。そこでクラスコは、管理する賃貸住宅を契約されたお客様に対し、「仲介手数料無料」とする支援と、契約開始から最大6ヶ月間の家賃を無料とする「住宅支援」を実施しました。
1月5日から3月末までの期間で、お部屋探しに来店された方は3,258組に上り、そのうち約1,000組が被災された方でした。そして、その約6割の方に賃貸物件の入居申し込みをいただくことができました。一人ひとりの状況に寄り添い、最適な支援を提供できたのではないかと感じています。
この支援を通じて、改めて痛感したのは、住まいの選択肢を提供することの重要性です。被災された方々は、心身ともに疲弊しており、複雑な手続きや費用負担が大きな障壁となります。仲介手数料の無料化や家賃の減免は、そうした負担を軽減し、新たな生活を始めるための一助になったはずです。
住宅購入費用の負担による新たな生活のサポート
賃貸住宅だけでなく、持ち家を失われた方への支援も必要です。そこでクラスコは、能登半島地震によって被災された方が新たな住居を購入する際、最大で100万円の購入費用を負担する支援を実施しました。
募集開始から約1ヶ月で、輪島市やかほく市で被災された2名の方から金沢市の物件購入のお申し込みがあり、支援させていただきました。この支援は、まだ始まったばかりですが、被災された方々が新たな生活をスタートするための、力強い後押しとなることを願っています。
4. クラスコの支援活動から見えた課題と教訓
今回の地震におけるクラスコの支援活動を通して、改めて多くの課題と教訓が見えてきました。
まず、情報伝達の難しさです。地震直後の混乱期には、電話やインターネット回線が寸断され、入居者様とのコミュニケーションが困難になりました。災害時にも確実に情報伝達ができるノーコードツール(たすけっと) に助けられました。
今回の支援は、応急的なものが中心でしたが、被災された方々の生活再建には、長期的な視点でのサポートが必要です。雇用、教育、医療など、様々な側面からの支援と連携が不可欠です。
そして、業界全体の連携 の重要性です。一つの企業だけでできることには限界があります。不動産業界全体が連携し、ノウハウや資源を共有することで、より 迅速な支援が可能になるはずです。
今回の経験は、私たちにとって、今後の事業活動を見直す上で非常に貴重な機会となりました。災害に強い住まいづくり、迅速な情報伝達体制の構築、地域社会との連携強化。これらの課題に真摯に向き合い、改善していくことが、私たちの使命だと改めて感じています。
5. 不動産業界が取り組むべき今後の対策
今回の能登半島地震は、私たち不動産業界に、未来に向けて取り組むべき多くの課題を突きつけました。被災地の復興支援はもちろんのこと、今後起こりうる災害に備え、業界全体で対策を講じていく必要があります。
テクノロジーを活用した防災・減災対策
近年、不動産業界においてもDX(デジタルトランスフォーメーション)が進んでいます。このテクノロジーを、防災・減災対策に活用していくことが重要です。
例えば、IoTセンサー を活用することで、建物の構造的な異常を早期に検知し、被害を最小限に抑えることができます。また、AI を活用したハザードマップの高度化や、避難経路の最適化なども考えられます。VR(仮想現実) を活用した防災訓練は、住民の防災意識を高める上で有効でしょう。
クラスコでも、これらのテクノロジーの導入を積極的に検討し、より安全・安心な住まいづくりを目指していきたいと考えています。
地域社会との連携強化
災害発生時には、行政や地域住民との連携が不可欠です。日頃から、地域社会とのコミュニケーションを密にし、信頼関係を築いておくことが重要になります。
例えば、地域の防災訓練への参加 や、災害時の役割分担の明確化 などが考えられます。また、地域のNPOやボランティア団体との連携 も、 迅速な支援活動を行う上で重要です。
クラスコは、地域に根ざした企業として、今後も地域社会との連携を強化し、災害に強い街づくりに貢献していきたいと考えています。
サステナブルな住まいづくりの推進
地球温暖化が進む現代において、災害リスクはますます高まっています。将来世代のためにも、環境負荷を低減し、持続可能な住まいづくりを推進していく必要があります。
例えば、省エネルギー性能の高い建材の利用 や、再生可能エネルギーの導入 などが考えられます。また、緑地を増やす ことは、ヒートアイランド現象の抑制にも繋がり、災害リスクの軽減に貢献します。
クラスコは、持続可能な社会の実現に向けて、サステナブルな住まいづくりを積極的に推進していきます。
6. 能登の復興、そして不動産業界の未来へ
能登半島の復興は、まだ始まったばかりです。道のりは長く険しいものになるでしょう。しかし、私たちは、今回の地震から得た教訓を活かし、より安全で安心な、そして持続可能な社会の実現に向けて、歩みを止めるわけにはいきません。
不動産業界は、人々の生活の基盤である「住まい」を提供するという、重要な役割を担っています。だからこそ、私たちは、常に変化する社会のニーズに応え、 最新技術を取り入れながら、未来の住まいづくりを追求していく必要があります。
今回の能登半島地震は、私たちに多くの課題を突きつけましたが、同時に、未来への希望も与えてくれました。被災地の方々の力強い姿、そして、復興に向けて立ち上がろうとする人々の熱意。それらは、私たちに勇気を与え、前に進む力を与えてくれます。
クラスコは、地元企業として、能登の復興に全力を尽くします。そして、今回の経験を活かし、不動産業界の未来を切り拓く一翼を担いたいと考えています。
7. まとめ:困難を乗り越え、より良い未来を築くために
能登半島地震は、私たちに多くの悲しみと困難をもたらしましたが、同時に、人々の絆の強さ、そして、未来を切り拓く力を教えてくれました。
クラスコは、今回の経験を教訓に、災害に強い住まいづくり、地域社会との連携強化、そしてサステナブルな社会の実現に向けて、より一層努力してまいります。
不動産業界の未来は、決して平坦な道ではないでしょう。しかし、私たちは、困難を乗り越え、より良い未来を築くために、常に挑戦し続けます。