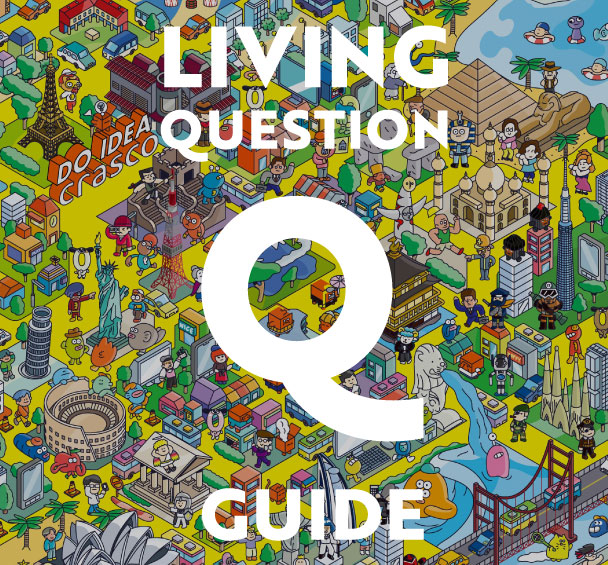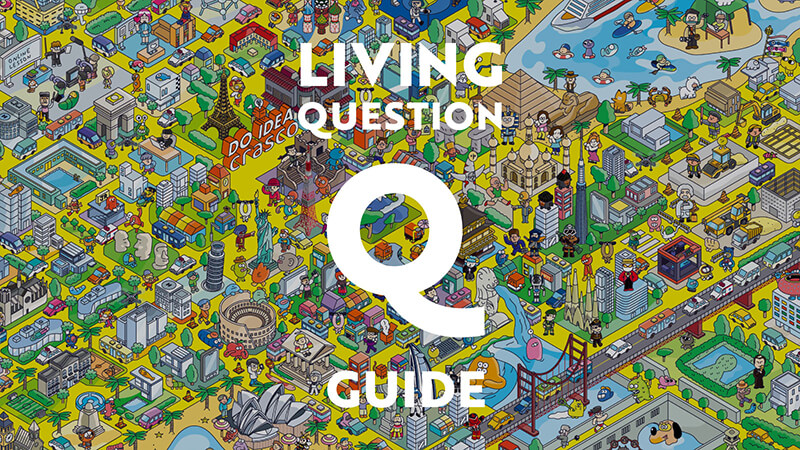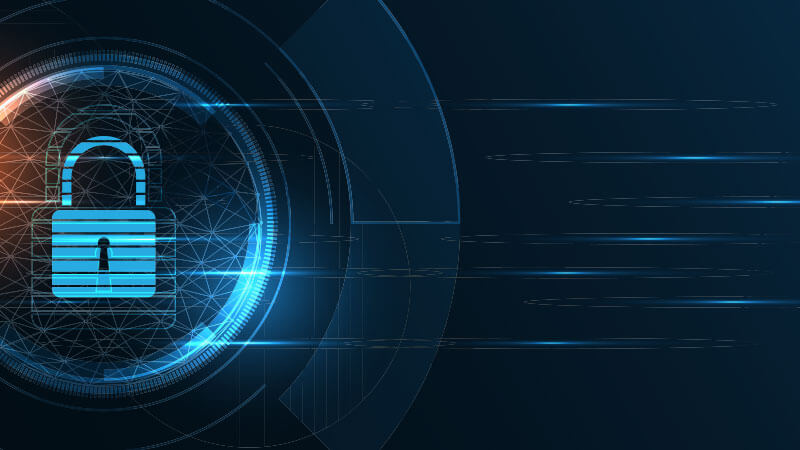成果をあげるために必要なのは 「取り組む」姿勢と方法だ
「成果をあげる人とあげない人の差は才能ではない。いくつかの習慣的な姿勢と、基礎的な方法を身につけているかどうかの問題である。しかし組織というものが最近の発明であるために、人はまだこれらのことに優れるに至っていない」(『非営利組織の経営』)
成果をあげる方法は、かつての一人だけの工房の時代と、今日の組織の時代では異なる。せっかく知識や技能を身につけても、まず初めに組織を通じて成果をあげる能力を向上させておかなければ役に立たない。
しかも、組織のニーズは非凡な成果をあげることのできる普通の人によって満たさなければならない。これこそ組織に働くものが応ずべきニーズである。
そもそも成果をあげる人間のタイプなど存在しない。
成果をあげる人たちは、気性や能力、仕事や仕事の方法、性格や知識や関心において千差万別である。共通点は、成果をあげる能力、つまり、なすべきことをなし遂げる能力を身につけていることだけである。
ドラッカーは成果をあげる人も、医者、教師、バイオリニストなどと同じように千差万別だという。成果をあげない人も同じように千差万別だという。成果をあげている人でも、個性や才能面では、成果をあげていない人と、たいした違いはないのである。
「成果をあげることは一つの習慣である。習慣的な能力の集積である。習慣的な能力は修得に努めることが必要である」(『経営者の条件』)
——————————————————————————————————————————————–
習慣的姿勢、すごく大事です
毎日、会社にギリギリに出社する人もいれば、朝早く出社する人もいます。
小さな約束を守るひともいれば、守れない人も・・・
毎日の習慣的姿勢が、大きな差になるように感じます
常に全力で仕事に取り組む人と、そうでない人、
絶対に差が開きます。