高い視点!?
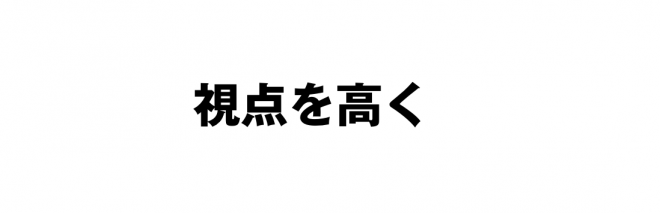
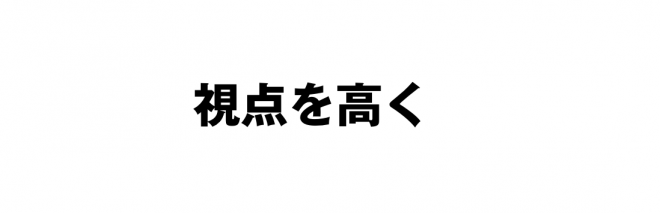
「えてして会社は、自らの経営幹部に対し、会社を生活の中心に据えることを期待する。しかし仕事オンリーの人たちは視野が狭くなる。会社だけが人生であるために会社にしがみつく」(『現代の経営』)
時折ドラッカーは、言いにくいことをズバリと言う。仕事オンリーだと、「空虚な世界へ移る恐ろしい日を延ばすために、自らを不可欠の存在にしようとする」と言う。
「バカな…」と否定してみても、心の奥深く行動の原点に近いところで、不可欠の存在にしようとする意識の動きを感じることがある。
一方が縛り、一方がしがみつく関係が生産的であるはずがない。「雇用関係とは、元々きわめて限定された契約であって、いかなる組織といえども、そこに働く者の全人格を支配することは許されない」 これがドラッカーの持論である。
そのうえ組織自体のためにも、組織の外の世界に関心を持つことを奨励すべきである。組織は組織のために存在するのではない。組織の外の世界のために存在する。
知性、感性、関心、価値観、その他あらゆるものについて、組織には多様性が求められている。そもそも詩人、収集家、音楽家を同僚にもつことはオツなものである。
「いまや会社は、社員を会社人間にしておくことが、本人のためにも会社のためにも危険であり、いつまでも乳離れできなくさせる恐れのあることを、認識すべきである」(『現代の経営』)
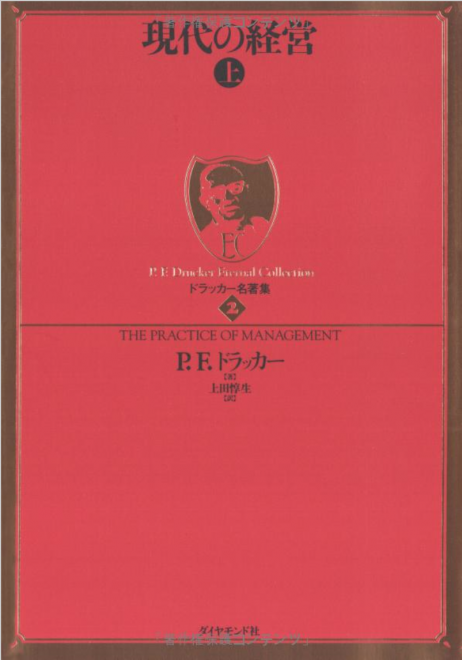
—————————————————————————————————–
これからは会社の時代ではなく、個人の時代だと思う。
会社という看板がなくなったら、何が出来るかが本当の力
本当の力を持っているか?が大事な時代
「われわれは未来についてふたつのことしか知らない。ひとつは、未来は知りえない、もうひとつは、未来は今日存在するものとも、今日予測するものとも違うということである」(『創造する経営者』)
ドラッカーは、ここで終わりにしない。続けて言う「それでも未来を知る方法は、ふたつある」と。
一つは、自分で創ることである。成功してきた人、成功してきた企業は、すべて自らの未来を、みずから創ってきた。ドラッカー自身、マネジメントなるものが生まれることを予測する必要はなかった。自分で生み出した。
もう一つは、すでに起こったことの帰結を見ることである。そして行動に結びつけることである。これを彼は、「すでに起こった未来」と名付ける。あらゆる出来事が、その発生と、インパクトの顕在化とのあいだにタイムラグを持つ。
出生率の動きを見れば、少子高齢化の到来は誰の目にも見えたはずだ。対策もとれたはずである。だが、高齢化社会がいかなる社会となり、いかなる政治や経済を持つことになるかを初めて論じたのはドラッカーだった。
———————————————————————————————————————————————————————
「未来を築くためにまず初めになすべきは、明日何をなすべきかを決めることでなく、明日を創るために今日何をなすべきかを決めることである」(『創造する経営者』)
将来をどのような「目標」を描くかで、今日することが変わる、目標って大事ですね!!!
「仕事に関する助言というと、計画から始めなさいというものが多い。まことにもっともらしい。問題はそれではうまくいかないことにある。計画は紙の上に残り、やるつもりで終わる。成果をあげる者は仕事からスタートしない。時間からスタートする」(『経営者の条件』)
彼らは計画からスタートしない。何に時間がとられているかを明らかにすることからスタートするという。
次に自分の時間を奪おうとする非生産的な要求を退ける。そして得られた時間を大きくまとめる。
ドラッカーは言う。
「時間は、借りたり、雇ったり、買ったりできない。供給は硬直的である。需要が大きくとも供給は増加しない。価格もない。限界効用曲線もない。簡単に消滅する。蓄積もできない。永久に過ぎ去り決して戻らない」。
時間の管理に取り組むには、まず時間を記録することが必要である。成果をあげるための第一歩は時間の記録である。
記録の方法を気にする必要はない。自ら記録してよい。秘書など他人に記録してもらってもよい。大切なことは、正しく記録することである。記憶によってあとで記録するのではなく、ほぼリアルタイムに記録することである。
「時間の記録をとり、その結果を毎月見ていかなければならない。最低でも年2回ほど3、4週間記録をとるべきである。記録を見て日々の日程を見直し、組み替えていかなければならない」(『経営者の条件』)
—————————————————————————————————————————————————————————
時間を記録をとり、分析すること、案外としていないですよね・・・
大事なことです。
「成功している組織には、あえて人を助けようとせず、人付き合いもよくない上司が必ずいる。愛想が悪くいつも不愉快そうでありながら、だれよりも多くの人たちを教育し育成する人、最も好かれている人よりも尊敬を得ている人がいる。部下と自らに厳しくプロの能力を要求する人がいる」(『現代の経営』)
そのような人は、高い目標を掲げ、その実現を求める。誰がどう思うかなど気にしない。何が正しいかを考える。頭のよさより、真摯さを重視する。
ドラッカーは、この真摯さなる資質に欠ける者は、いかに有能で人付き合いがよくとも、組織にとって危険な存在であり、上司として、紳士として不適格であるという。真摯さに欠ける者が跋扈するとき、組織は死への道をたどる。
リーダー的資質など存在しないと断言するドラッカーが、リーダーが持つべき唯一の資質として挙げるものも、この真摯さという資質である。
人は人の不完全なることを許す。ほとんどの欠陥を許す。しかし一つの欠陥だけは許さない。それが真摯さの欠如である。
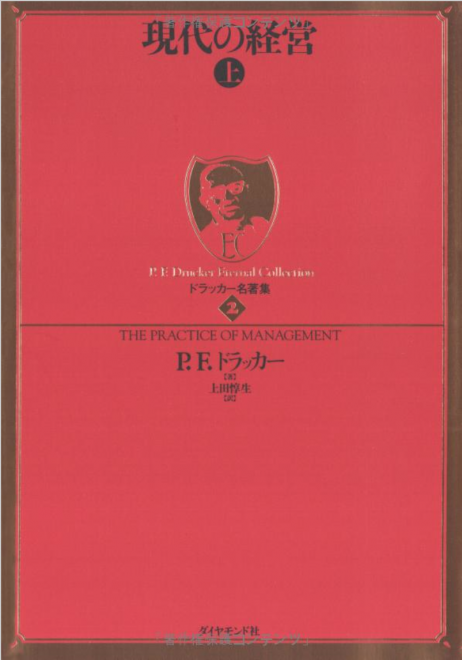 」(『現代の経営』)
」(『現代の経営』)
—————————————————————————————————-
ドラッカーの言葉で一番衝撃を受けた言葉です。
私は常にこの真摯さを意識しています。
その人が成長出来るために、私が出来る範囲のことを精一杯伝えていきたいと思っています。