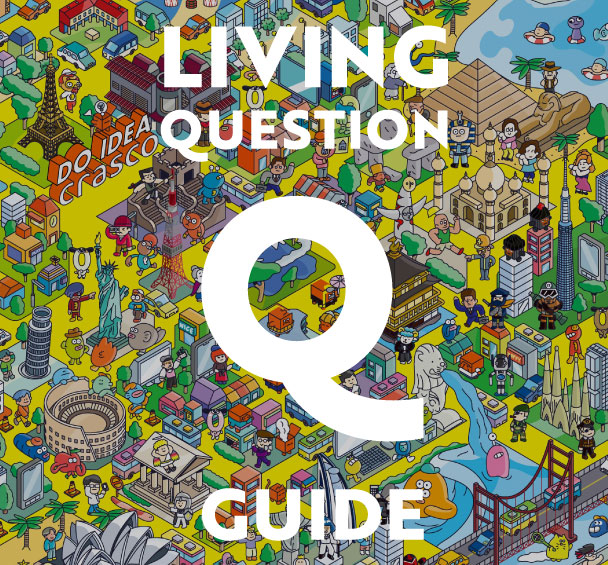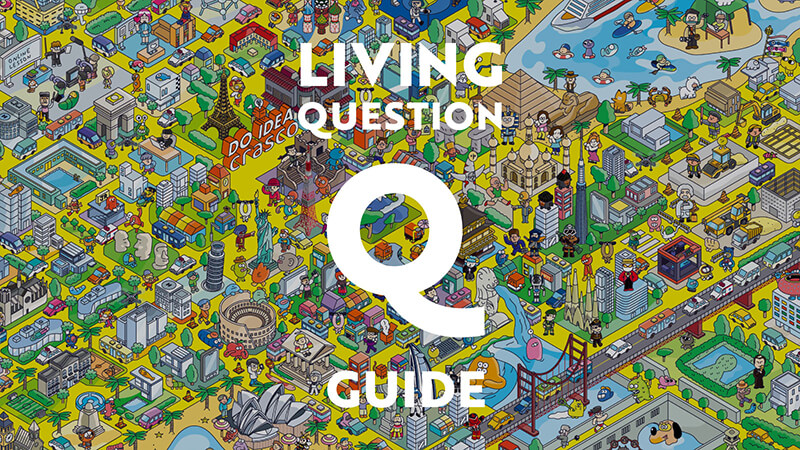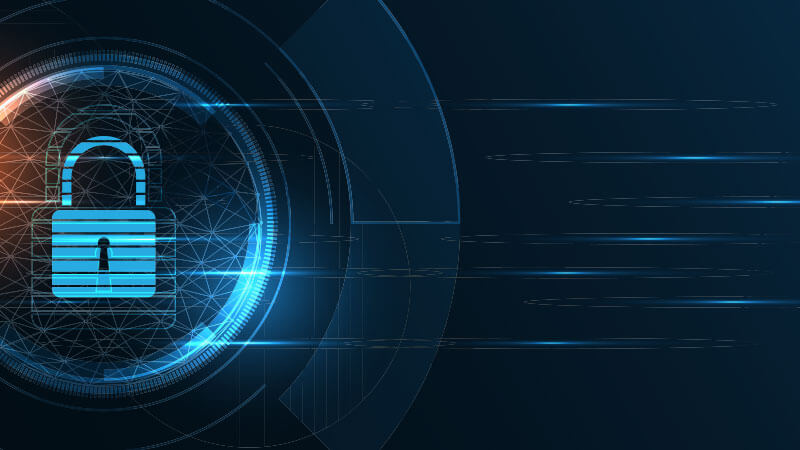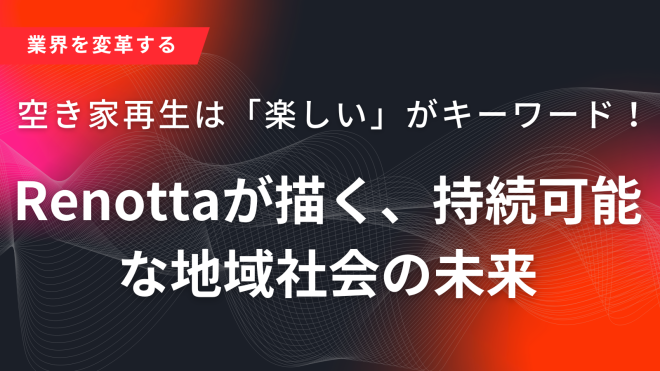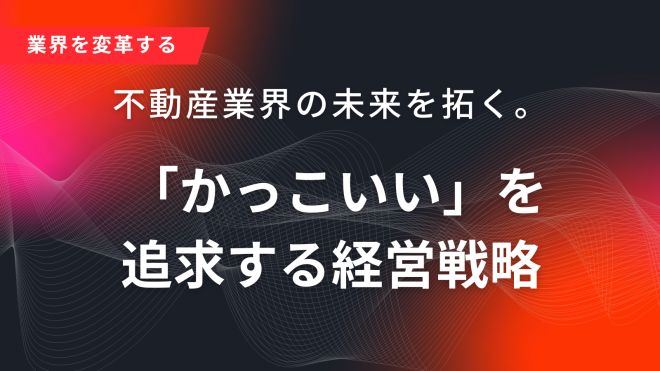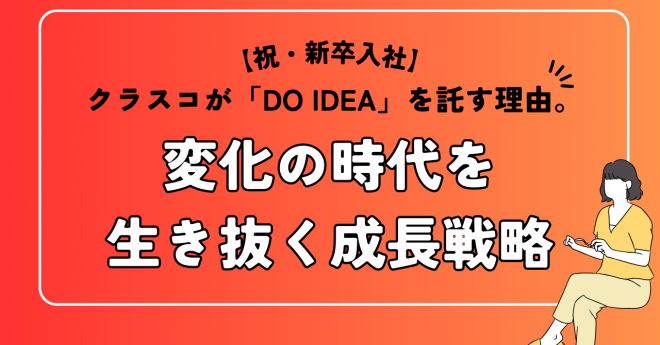「運がいい」を科学する。「DO IDEA」が導く幸運の法則
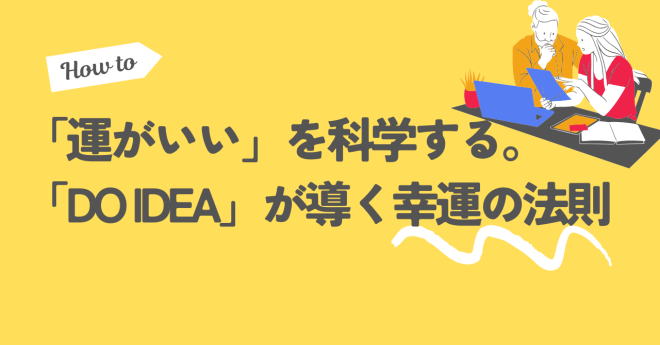
皆さん、こんにちは。株式会社クラスコ代表取締役社長の小村典弘です。
今日は、少し趣向を変えて、皆さんと「運」というテーマについて深く掘り下げてみたいと思います。
私自身、振り返ってみると、本当に運が良い人生を送らせていただいていると感じています。もちろん、決して平坦な道のりばかりではありませんでしたが、いつも不思議と良いタイミングで人との出会いに恵まれたり、困難な状況を乗り越えるためのヒントが舞い込んできたりと、幸運の女神が微笑んでくれたと感じる瞬間が数多くありました。
そんな私が、先日、ある書籍を読みました。「科学がつきとめた運のいい人はどんな人なのか」というタイトルに、思わず引き込まれてしまいました。科学的な視点から「運」を解き明かすというアプローチに、経営者として、そして一人の人間として、強い興味を覚えたのです。
書籍を読んでみると、そこに書かれていた内容は、私がこれまで肌で感じてきたことと、驚くほど合致していました。まるで、私の経験を科学的に裏付けられたかのような感覚に陥り、非常に興味深い体験でした。
今日は、その書籍の内容を参考にしながら、皆さんと共に「運」という不思議な力について、そして、どうすれば私たちはもっと「運の良い人」になれるのかについて、深く考察していきたいと思います。
■運とは、決して偶然や神秘的な力だけではない
書籍の著者は、運というものを、正体のない漠然としたものではなく、私たちの思考や行動を少し変えることで、意図的に向上させることができると説いています。これは、私が常々考えていることと非常に近いです。運が良い人は、ただ待っているだけではなく、自ら幸運を引き寄せるための行動を無意識のうちに取っているのではないでしょうか。
そして、著者が提示する運を良くする方法は、決して難しいものでも、特別なものでもありません。それは、私たちが日々の生活の中で意識すれば、誰にでも実践可能なことです。この書籍を読むことで、皆さんも、運を自らの力で手に入れるためのヒントを掴んでいただけたら幸いです。
■科学がつきとめた、運の良い人々の特徴
書籍によると、運の良い人々には、特定の行動パターンや考え方が共通しているそうです。それは、彼らが自分の個性を深く理解し、その個性を最大限に活用する方法を知っているということです。
例えば、攻撃的な性格の人は、一般的にはネガティブな印象を持たれがちですが、運の良い人は、その特性を弁護士のように競争的な分野で活かすことができると言います。自身の持つ特性を理解し、それをポジティブな方向に転換する力。これは、運の良い人が持つ重要な要素の一つかもしれません。
私自身を振り返ってみても、決して特別な才能があったわけではありません。むしろ、人よりも不器用で、時間がかかるタイプだったと思います。しかし、自分の強みと弱みを理解し、強みを活かせる場所で努力を続けたことが、結果的に運を味方につけたのかもしれません。
■ありのままの自分を受け入れることの重要性
書籍の中で特に印象的だったのは、「人は自分を変えることによって運を悪くすることがある」という一節です。これは、私自身も深く共感するところです。
私たちは、社会や周囲からの期待に応えようとするあまり、本来の自分を押し殺し、無理に自分を変えようとすることがあります。しかし、それは、まるで自分の足に合わない靴を履いて歩くようなもので、無理が生じ、結局は良い結果に繋がらないことが多いのではないでしょうか。
運の良い人は、自分の本来の性質を受け入れ、それを生かすことが、運を良くする近道であることを知っているのかもしれません。自分らしさを大切にすること。それは、運を引き寄せるための第一歩なのかもしれません。
■自分だけの「しあわせのものさし」を持つ
書籍では、運の良い人々は、他人とは違う、自分なりの幸福を測る基準を持っていると指摘しています。
現代社会は、とかく他人と比較しがちな傾向があります。「年収はいくらか」「どんな地位にいるのか」「どんな暮らしをしているのか」。私たちは、無意識のうちに、他人と比較することで自分の幸福度を測ろうとしてしまいます。
しかし、幸福の形は人それぞれです。他人にとっての幸せが、自分にとっての幸せとは限りません。運の良い人は、そのことを深く理解しており、世間の評価に左右されることなく、自分にとって何が幸せなのかを明確に知っているのではないでしょうか。そして、その「しあわせのものさし」に基づいて行動するからこそ、彼らは常に満たされた状態でいられるのかもしれません。
私自身も、経営者として、常に数字や外的要因に注意を払う必要がありますが、最終的に重要だと考えているのは、社員が幸せに働いているか、お客様に喜んでいただけているか、そして、それが社会に何らかのポジティブな影響を与えているかという点です。自分なりの「しあわせのものさし」を持つこと。それは、運に左右されない、持続可能な幸福を得るための鍵となるでしょう。
■運は、自ら作り出すもの
書籍は、運は決して外部からの授かり物ではなく、自分で決めるものだと断言しています。
「自分は運が良い」と信じる人は、困難に直面しても、そこで諦めることなく、努力し続ける余地があります。なぜなら、彼らは、最終的には運が味方してくれると信じているからです。その前向きな姿勢が、さらなる幸運を引き寄せるのかもしれません。
逆に、「自分は運が悪い」と思い込んでいる人は、少しの困難にもすぐに諦めてしまいがちです。その後ろ向きな思考が、せっかくのチャンスを逃してしまう原因になっている可能性もあります。
運が良いと信じること。それは、まるで自動操縦のように、私たちを良い方向へと導いてくれる力を持つのかもしれません。
■運の良い人々との関わり
書籍の中で興味深かったのは、運の良い人の近くにいることで、その行動パターンを学び、自分自身も運が良くなる可能性があるという指摘です。
これは、「類は友を呼ぶ」という言葉にも通じるかもしれません。ポジティブなエネルギーを持つ人の周りには、自然とポジティブな出来事が集まりやすいものです。運の良い人の思考や行動パターンを間近で学ぶことは、私たち自身の運を向上させるための、効果的な方法の一つと言えるでしょう。
私自身も、これまで多くの素晴らしい人たちとの出会いに恵まれました。彼らの前向きな姿勢や、困難に立ち向かう不屈の精神は、私にとって大きな学びとなり、自身の運を形成する上で、重要な役割を果たしてくれたと感じています。
■他者との共生という視点
書籍では、運の良い人は他者を思いやり、共同体として生きることが重要だと説いています。利他的な行動は、巡り巡って自分自身の幸運につながるという考え方は、東洋的な価値観にも通じるものがあります。
私たちは、一人で生きているわけではありません。周囲とのつながりの中で生きています。他者を思いやり、助け合うことは、良好な人間関係を築き、信頼を得ることにつながります。そして、その信頼が、思わぬ形で幸運をもたらしてくれることもあるでしょう。
利他的な行動は、単に道徳的な行為としてだけでなく、運を良くするための実践的な戦略としても、非常に有効なのかもしれません。
■セレンディピティを味方につける
書籍は、偶然の幸運をキャッチする能力、セレンディピティを高めるためには、明確な目標を持つことが重要だと指摘しています。
これは、一見すると矛盾しているように感じるかもしれません。偶然の幸運は、予期せぬ形で訪れるものだからです。しかし、明確な目標を持っている人は、アンテナが立っている状態です。偶然の出来事の中に、自分の目標達成に繋がるヒントやチャンスを見つけ出すことができるのです。
私も、常に明確な目標を持ち、それに向かって行動するように心がけています。その過程で、思わぬ出会いや発見があり、それが新たなビジネスのチャンスに繋がった経験は数えきれません。セレンディピティは、積極的な姿勢によって引き寄せられるものなのかもしれません。
■ゲームを降りないことの重要性
書籍の結論として、運の良い人は、自分の夢や目的に対して、長期的な視点を持ち、途中でゲームを降りないと述べられています。
人生は、決して単調なものではありません。良いこともあれば、悪いこともあります。運の良い人は、プラスとマイナスの出来事を均等に受け入れ、一時的な感情に左右されることなく、自分の夢や目標に向かって進み続けます。
途中で諦めてしまえば、そこでゲームオーバーです。しかし、諦めずに続ける限り、チャンスは必ず巡ってきます。運の良い人は、そのことを深く理解しているのではないでしょうか。
私も、経営者として、何度も困難に直面し、諦めそうになったことがあります。しかし、その度に、長期的なビジョンを思い返し、再び立ち上がってきました。結局、最後に笑うのは、ゲームを降りなかった人なのかもしれません。
■まとめ:運を良くするための、科学的なアプローチ
この書籍を読んで、改めて感じたのは、運は決して不可解なものではなく、私たち自身の心の持ち方や行動に大きく左右されるものだということです。
自分の特性を理解し、それを活かすこと。
自分なりの幸福の基準を持つこと。
運が良いと信じること。
運の良い人と関わること。
他者を思いやること。
明確な目標を持つこと。
そして、決して諦めないこと。
これらの要素は、どれも特別な才能や富を必要とするものではありません。日々の生活の中で、少し意識を変えるだけで、誰にでも実践可能です。
もし、皆さんが「最近、運が悪いな」と感じているのであれば、この書籍で紹介された内容を参考に、自身の思考や行動を振り返ってみてはいかがでしょうか。少しの変化が、皆さんの運命を大きく変えるかもしれません。
私たちクラスコは、不動産を通じて、お客様の「GO FUN LIFE」を実現することを目指しています。それは、単に住居を提供するだけでなく、そこに住む人々の人生を豊かにする、様々な価値を提供することを含んでいます。
運が良い人生を送るためには、周囲の環境も重要です。私たちは、お客様にとって、常に前向きで明るい環境を提供できる存在でありたいと考えています。
これからも、お客様の「GO FUN LIFE」をサポートするために、革新的なサービスを提供し続け、共に成長していきたいと思っています。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。